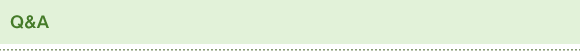
|
����ʊ֘A
|
|
| Q. | �o�b�e�Ǎ����̗��_�� |
| A. | �Ǎ����̊O���ɑ��ꂪ�ݒu�ł��Ȃ��ꍇ�A�]���H�@�ł͍|���̖��^�g���g�p���Ă��܂����A�{�H�@�̓R���N���[�g���̖��^�g�Ƃ��Ă��܂��B���|���^�g�͑ϋv���̖�肩��h�ւ���ă��b�L�Ȃǂ̕�C���K�v�ƂȂ�܂����A�i���̐������R���N���[�g���̃v���L���X�g�^�g���g�p���邱�Ƃŕ�C��Ƃ����Ȃ��Ȃ�A���C�t�T�C�N���R�X�g�̏k�����\�ƂȂ�܂��B |
| Q. | �u�e�q�b�Ƃ͉��̗��̂� |
| A. | �u�e�q�b�F���������������@�����������@���������������������@�������������������������@�������������������@�@ �i�r�j�����@�ۂ�⋭�ނƂ��č��������Z�����g�����ޗ��j |
| Q. | �|���^�g���A�����R�X�g�͍����̂� |
| A. | �ݗ��H�@�Ƃ̔�r�ł������Ƃ���A��{�I�ɂ́A�|���^�g��������Ȃ�܂��B�A�����i�̉��i�́A�A�������A���얇���A�`��i�^�g��j�ɂ��A�قȂ�܂��̂ŁA���ۂ̕����ɓ������ẮA���ς�˗������肢���܂��B�i����20�N11�����_�ŁA�|�ޒP���̏㏸�A�h�K�����i���b�L���j�P���̏㏸�ɂ��A�|���^�g�̐����͍����Ȃ��Ă��܂��B�j |
|
���v�֘A |
|
| Q. | �o�b�e�ł̒P�ʎ��ʂ� |
| A. | �P�ʎ��ʁ�21.0��N/m3 �S�R���N���[�g�ł́A24.5��N/m3�ł����APCF�ł͑@�ە⋭�����^���Ŗ��؍\���ł��邽�߁A21.0��N/m3�@�ƂȂ�܂��B�i�Ȃ��A�v��́A�o�b�e�ł̑̐ς��Am����̐v�d�Ƃ��܂��B�j |
| Q. | �o�b�e�ł̍ő吻��\���@�� |
| A. | ��2550mm�~����1500mm�~����30mm�ł��B |
| Q. | �o�b�e�ł̕W���T�C�Y�� |
| A. | �o�b�e�ł̊��t��2.0m��W���Ƃ��܂��B���i����1990�����Ƃ��Ėڒn����10mm�݂��܂��B�����́A�Ǎ����O�ʍ����{�㑤�̏o��50mm+�����̏o��i��������p�j30mm��W���Ƃ��܂��B30mm�̌������́A�^�g�����Ƃ��āA�O���ɔz�u���܂��B |
| Q. | �����R�O�����͉����猈�܂��Ă��邩 |
| A. | �������@�y�э\������ŏ����������肵�܂����B�\���I�ɂ́A�����ɃC���T�[�g�ߍ���ł���܂��̂ŁA����ȏ㔖�����邱�Ƃ͏o���܂���B |
| Q. | ���i�̏d���͂ǂ̂��炢�� |
| A. | 1�u������630N(��63kg)�ł��̂ŁA�W���I��PCF��(1.2m�~2m)��1��������1510N(��151kg)�ɂȂ�܂��B |
| Q. | �����̃f�t�H�[���̌��ʂ� |
| A. | �f�t�H�[�����i�ʉ��j���ŕt���������߂Ă��܂��B�������A�c���^�̌^�g�����̂��߁A�L���f�ʂɂ͍l�����Ă��܂���B |
| Q. | ����n��Ŏg�p�͉\�� |
| A. | �����x�����^�����k���Ȑ��i�ł��̂œ��Q�A���Q�������Ȃǂ̑ϋv���ɂ�����Ă��܂��B�����Z�������ł�100�N��̎��Z�l��0mm�œ��ʂɐZ�����邱�Ƃ́A�قƂ�ǂȂ����߁A����n��̂ق����A���\�����܂��B |
| Q. | �V�݂̂q�b���łł̎g�p�͉\�� |
| A. | �V�݂̂q�b�^�g�ł́A�Ǎ����̒���o�����������݂��邱�Ƃ���A�����b�g�͏��Ȃ��A�̗p���т͌����܂��D�������A�H���Z�k�����_���Ŋ����ƂȂ��Ă������ϋv�����l�����č̗p�ɂȂ����P�[�X�A�Ǎ����e�ɖ�`�|�����r������A�ؐ��^�g�̐ݒu������ȏꍇ�̗̍p�ƂȂ����P�[�X��������܂��B�R�X�g�팸�ɂ͂Ȃ�܂��g�p���邱�Ƃ͉\�ł��D |
| Q. | �Ǎ����̕�C�Ƃ��Ďg�p�\�� |
| A. | �q�b���ł̕Ǎ����̎��тƂ��Ă͂Q������܂��B�ϋv���̌�����܂߂���C���\�ł��B |
| Q. | �S�����ł��g�p�\���H |
| A. | �S�����ł̎{�H���\�ł��B�i���т�����܂��j�������Ȃǂł́A�ؐ��^�g������ȉӏ��Ń����b�g������܂��B�܂��A���ˉ��H���ł́A��L�ʐς����Ȃ��A�����ݒu����ƍ����������Ȃ邱�Ƃ���v���L���X�g����}�������������܂��B |
| Q. | �ȗ����a�͂ǂ̒��x�܂Ŏg�p�\�� |
| A. | �q���R�O�O���x�܂ʼn\�ł��B PCF�ł͒����I�Ȑ��i�𑽊p�܂�ɂ��đΉ����܂��B |
| Q. | ����Őؒf��E�����͉\�� |
| A. | �R���N���[�g�J�b�^�[�ɂ��ؒf�A�h�����ɂ�錊�������e�Ղɏo���܂��B�i�o�b�e�ł͖��ł��̂œS�؈ʒu���l������K�v�͂���܂���j |
| Q. | �[���̉����Ή��͉\�� |
| A. | �\�ł��B���`��c�f���z���}���z�̏ꍇ�́A�[���������Ɏd�グ�邱�Ƃ�����͉\�ł��B |
| Q. | ����ł̔[�i�܂łɂǂ̒��x���Ԃ��K�v�� |
| A. | �{�H�����ɂ����܂����A�v�P��������R�������x�͕K�v�ł��B�i�����@200����z��j |
| Q. | �v��Ȃ����x�͂ǂ̒��x�� |
| A. | �v����x�F���k���x��ck��50.0N/�o2�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Ȃ����x��bK��12.0N/�o2 |
| Q. | ���d�ɖ��͂Ȃ��� |
| A. | ���d��1kN/m(��100kg/m�j�ȉ��̑����ł��邽�߁A�|���̏ꍇ�̎包�f�ʂ��������Ƃ͂���܂���B�������A���Œ���o�����̐v�ɂ����Ă͎��d�Ƃ��čl������K�v�͂���܂��B |
| Q. | �����͂���̂��H |
| A. | ���i�Ƃ��Ă̓����͂���܂��AVFRC�͓���ȕ��@�Ő������Ă��܂��B�֘A�����Ƃ��Ă͉��L�̓���������܂��B �E������3636960�� �E�������ҁF���H�Ɗ�����ЁA���C�R���N���[�g�H�Ɗ������ �E�����̖��́F�n�[�t�v���L���X�g�Ǖ��ށA����т��̃n�[�t�v���L���X�g�Ǖ��ނ�p�����y�،��z�H�@ |
| Q. | �ڒn���̍\���͂ǂ��Ȃ��Ă��邩 |
| A. | PCF�łɐ茇�����݂��Ă���A�o�b�N�A�b�v�ނ��˂������Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B�o�b�N�A�b�v�ސݒu��A�R�[�L���O�ޓ��ŃV�[�����܂��B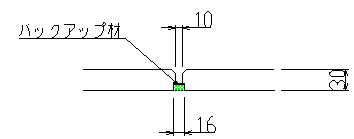 |
| Q. | �]���H�@�̍|���^�g�ɔ�ׂĕi���͌��シ�邩 |
| A. | �]���Z�p�̍|���^�g�͌��݂̍ہA�h���܂��͈������b�L�ɂ��h�K�������{����܂��B�������A����̍\�������ώ@����ƍ|���^�g�̎K�т������i�s�����ς˂���A�R���N���[�g�Ƃ̔������Ă�����̂������Ό����܂��B�|���^�g�͍\���f�ʂƂ��čl�����Ă��Ȃ����߁A���x��̖��͂���܂��A���Ϗ�h�K�����i�h�ւ����j���{����܂��B�{�Z�p�͑ϋv���ɗD�ꂽ�@�ە⋭�Z�����g�����ޗ��^�g�Ƃ��Ďg�p���Ă��邽�߁A���̂悤�ȎK�т����������肪�����A�ێ��Ǘ����ɗD��Ă��܂��B |
| Q. | �]���H�@�̍|���^�g�ɔ�ׂđϋv���͌��シ�邩 |
| A. | �ϋv���͌��サ�܂��B�]���Z�p�̍|���^�g�͓h�ւ���ă��b�L��C���K�v�ƂȂ�܂����A�{�H�@�͑@�ە⋭�Z�����g�����ޗ����g�p�����^�g�ł��邽�ߓh�ւ��͕K�v����܂���B�{�H�@�̂o�b�e�łɊւ��ẮA�����������A�����Z�������y�щ��Q�ɑ��Ă͐Z�����ɂ��R���N���[�g���̉������C�I���̌��|���̊g�U�W���������тɁA�d�o�l�`�@�ɂ��R���N���[�g���̌��f�̖ʕ��͎������@�ɂ�茟���Ă��܂��B |
|
���ޗ��E����֘A |
|
| Q. | �o�b�e�ł̍ޗ��͉����g�p���Ă���̂� |
| A. | �����x�̃����^���Ƀr�j�����@�ۂ��������Ă��܂��B |
| Q. | ���i�Ɋ܂܂��̂͂ǂ��܂ł� |
| A. | PCF�ŋy�ю��t������݂̂ł��D�i�{�̕t�����t�������C�������ł̎~�����̗n�ځC�{���g���ߕ��ނ͊܂܂�܂���B |
|
���{�H�֘A |
|
| Q. | �N�ł��ȒP�ɐݒu�ł���̂� |
| A. | ��������H�ŋ����ː݂̌���o����������ł�����ݒu�͏o���܂��B�܂��{�H�ɓ������Ă͎{�H�v�̏����쐬���A������v���܂��B |
| Q. | ��������͕s�v�� |
| A. | ���ꖳ���ł̎{�H�͉\�ł����A���S�q���@�A���y��ʏȁ@���ݍH�����O�ЊQ�h�~���v�ԓ��������A��R�Ҕ�Q�A��Ǝ҂̈��S������{����K�v�͂���܂��B |
| Q. | PCF�ł̕\�ʂɂ̓Z�p���[�^�Ղ͏o�Ȃ��̂� |
| A. | �o�b�e�Ŗ{�̂ɂ́A�C���T�[�g�i�ڃl�W�j�����ߍ���ł��邽�߁A�O���̃Z�p���[�^�Ղ͔������܂���B |
| Q. | �}���{�H�ł̎��т͂��邩 |
| A. | �}���{�H�Ƃ��Ă̎��т͂���܂��B����o���H�@��ꊇ�ː݁A�������ŕ��ɍ��킹�Ēn�g���ɐݒu�����\�ł��B |
| Q. | �Փˎ��ɃR���N���[�g�j�Ђ���U���Ȃ����R�� |
| A. | PCF�ł̓r�j�����@�ۍ����ɂ���Ր�������̂ŁA�Փ˂ɂ��R���N���[�g���j�Ă�PCF�ł͔�U����悤�Ȕj��͂��܂���B |
| Q. | �o�b�e�ł̐ݒu���|�͂ǂ̒��x�����߂悢�� |
| A. | �u�����ːݍH���̐ώZ�i�����Q�O�N�x�Łj�i�Ёj���{���@�B������v��2.8�|�����ōH�[�������ōH�[���|��t�H���|�Ɠ����ł��̂ŁA�Q�Ƃ��Ă��������B |